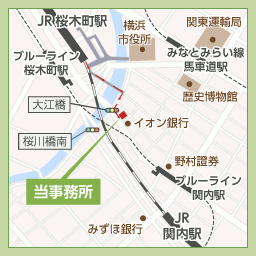相続の豆知識(法定相続)
Q.先日、夫が亡くなりました。
私と夫の間には、子どもが2人います。夫の父(義父)も健在で、5人で暮らしていました。夫には兄がおり、夫は、兄(義兄)と一緒に働いていました。
遺言は遺されていませんでした。
夫の遺産を相続するのは、誰でしょうか。夫の父(義父)や、夫の兄(義兄)も相続人ですか。
遺産分割協議
遺産の分割は、亡くなった方が遺言を残しており、遺言で、誰が、何を、どれだけ相続するかが決めてあれば、原則として、その遺言の内容に従うことになります。
遺言がない場合には、相続人の間で、誰が、何を、どれだけ相続するかを話し合うことになりますが、この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では、法定相続人全員が合意しているのであれば、自由に遺産を分ける(法定相続分とは異なる遺産分割をする)こともできますが、分け方のルールとなるのが、民法に定められている法定相続分です。
法定相続
遺言を残さずに誰かが亡くなった場合、その亡くなった方の財産を、誰がどのような割合で引き継ぐかは、民法に定めがあります(法定相続)。
配偶者は、常に相続人となり、そのほかに、①子、②子がいない場合は直系尊属(父母等)、③子も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が、配偶者とともに、相続人となります。
子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分と配偶者の相続分は、2分の1ずつです。子が複数人いるときは、人数で均等割りをします(民法第900条4号)。
ご質問の場合は、お子さんがいらっしゃいますので、夫の父(義父)や夫の兄(義兄)は相続人になりません。
したがって、相続人は、配偶者であるあなたと、子ども2人です。
そして、子ども2人で、子の相続分を半分ずつ、相続します。
法定相続人の決定方法
亡くなった方(被相続人)の配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)。
↓
第1順位 子は、相続人となります。
↓
第2順位 子がいない場合には、被相続人の直系尊属(父母等)が相続人となります。
↓
第3順位 子がおらず、かつ、直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
Point
第1順位の人がいたら、第2順位の人は相続人になりません。
また、第1順位、第2順位の人がいたら、第3順位の人は相続人になりません。
法定相続分
法定相続人の相続分(法定相続分)は、民法第900条に、順位によって定められています。
⑴ 配偶者と子が相続人になる場合
配偶者と子は2分の1ずつの割合で相続します(民法第900条1号)。
なお、子が複数人いる場合には、子らは、子の相続分である2分の1を均等に分割して、相続します(民法第900条4号)。
⑵ 配偶者と直系尊属が相続人となる場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で相続します(民法第900条2号)。
⑶ 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1の割合で相続します(民法第900条3号)。
相続に関する問題は、弁護士にご相談ください
遺言を遺して亡くなる方は、それほど多くありません。多くのケースでは、遺族で話し合って、誰が、何を、どれだけ相続するか話し合うことになります(遺産分割協議)。
- 相続が開始したが、遺言書がない。
- 相続人が誰かわからない。
- 相続人同士で話し合いがまとまらない。
- 相続人が非協力的または音信不通(行方不明)のため、協議が進められない。
相続に関する問題は、弁護士にご相談ください。