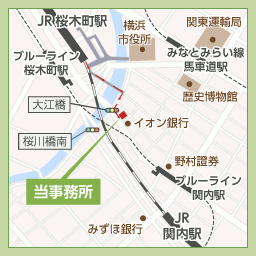相続の豆知識(葬儀費用)
Q.父が亡くなりました。
兄妹がいますが、誰も葬儀をしないので、自分が挙げました。葬儀費用は、誰が負担すべきでしょうか。
父のお骨は、長男である兄に引き取ってもらいたいと思っています。
一般的な考え方
葬儀費用を誰が負担すべきかについては、法律上、明確な定めがありません。
いくつか考え方がありますが、一般的には、喪主(葬儀を挙げた者)が葬儀費用を負担すると考えられています。
葬儀を行うか否か、葬儀を行うにしても、規模をどの程度にして、どれだけの費用をかけるかについては、もっぱら葬儀を挙げる方が決定して、実施することからすると、この考え方が自然ということになるでしょう。
他方で、人の身体が、その死亡により遺体・遺骨となった場合、単なる物として所有権の客体となるかについて、通説・判例は、これを肯定しており、遺体・遺骨の所有権の帰属者については、祭祀主宰者に帰属するとされています(最高裁平成元年7月18日判決)。
喪主と祭祀主宰者は、必ずしも一致するわけではありません。祭祀主宰者は、第一に被相続人の指定、指定がないときは、第二に地域の慣習、第三に指定も慣習もない場合には家庭裁判所の審判により決められることになります(民法第897条)。
喪主が葬儀費用を負担しないケース
遺言書に記載がある場合
亡くなった方が、遺言書を遺していて、遺言書に「葬儀費用は遺産のなかから払うように」と記載されていれば、基本的には、それに従う必要があります。
亡くなった方があらかじめ自らの葬儀に関する契約(生前契約)をしていた場合
亡くなった方が、葬儀社に、葬儀の予約をしていることがあります。
こうした場合、葬儀費用は、相続財産から支払うように契約されていることが多いです。
相続人の間で合意ができた場合
相続人の間で、葬儀費用の負担について、話し合って、合意ができるのであれば、その内容は、自由に決められます。
Point
相続人の間で話がまとまるのであれば、葬儀費用は、亡くなった方の遺産(相続財産)から支払うこともできます。
以前は、被相続人が亡くなると、その人名義の預貯金口座は凍結されてしまい、遺産分割が完了するまでは口座の出入金ができませんでした。
しかし、2019年7月1日の民法改正によって、「相続預貯金の仮払い制度」が新設され、この手続きを行うと、凍結中の口座が解除され、一定額までなら、遺産分割確定前に、亡くなった方の預貯金から引き出しができるようになりました。
亡くなった方の遺産(相続財産)から葬儀費用を支払った後は、遺産をどのように分割するのか、例えば、残った遺産を公平に分割するか、相続財産から差し引いた葬儀費用は喪主の負担とするのか等を、遺産分割協議書にまとめておきましょう。
相続に関する問題は、弁護士にご相談ください
現在は、相続人間で法定相続分に応じて公平に遺産を分割するケースが多くなっていますので、葬儀費用も、相続人間で公平に負担するのでなければ、喪主の負担が過大となってしまいます。
- 葬儀費用の負担について、相続人間で意見が対立している。
- 葬儀費用について、遺言書に記載したい。
- 葬儀費用について、相続人間で事前に協議したい。
- 相続財産から、葬儀費用を支払いたい。
相続に関する問題は、弁護士にご相談ください。