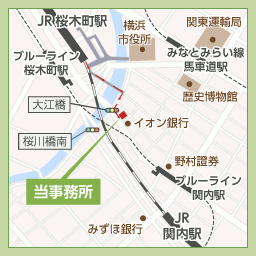相続の実務(特別受益-挙式費用-)
Q.父が5000万円を残して亡くなり、母、私(姉)、妹の3人が相続を受けることになりました。
私も妹も結婚をしていますが、父は、私の結婚に関してだけ、挙式費用として100万円を援助しています。挙式から時間が経った今でも妹はそのことを気にしているようで、相続の話でも、私の取り分を100万円減らそうと提案してきます。
確かに、私は挙式費用100万円の援助を受けていますが、相続の場面で、私の取り分が100万円減らされなければならないのでしょうか。
特別受益
相続の場面では、亡くなった方(被相続人)の残した財産や負債を相続人が引き継ぐことが一般的ですが、生前に被相続人が相続人に贈与をしたこと(特別受益)や、相続人が被相続人のお世話をしたこと(寄与分)なども精算され、具体的な相続分が決定されます。
生前に被相続人が、相続人に対し金銭等を贈与した事実は、被相続人の相続人に対する特別受益として見られることがあり、相続分の前渡しとして、相続財産に組み込んで相続分を検討します。
仮に、本件で挙式費用が特別受益に当たらない場合と、当たる場合では、以下のような相続分の変化が生じます(法定相続分は、母2分の1、私・妹は各4分の1)。
| 挙式費用が特別受益に当たらない場合 | 挙式費用が特別受益に当たる場合 |
|---|---|
| 母:5000万円÷2=2500万円 私:5000万円÷4=1250万円 妹:5000万円÷4=1250万円 |
母:5100万円÷2=2550万円 私:5100万円÷4-100万円=1175万円 妹:5100万円÷4=1275万円 |
このように、挙式費用が特別受益に当たるか否かにより、相続分に差が生じます。
それでは、挙式費用は、特別受益に該当するのでしょうか。
挙式費用
民法第903条1項は、「婚姻のため」贈与を受けた場合には、この費用は特別受益に該当するとしています。
しかし、実務上、挙式費用(結婚式、披露宴)に関しては、婚姻する当事者のためという側面よりも、親の社交上の出費としての性質が強いとみられることが多く、一般的には特別受益には該当しないとの判断が多くされます。
ただし、これはあくまで一般論であり、判断基準としては、その地方の慣習、婚姻する当事者の地位や資産、支出する地位や親の資産、支出する額の大きさ、他の相続人への同名目での出費の有無などにより複合的に決定されます。
その他の婚姻に際する費用について
上記のように、挙式費用は、親の社交上の出費とみられることを理由として、一般的に特別受益には当たらないと判断されていますが、結婚指輪や新婚旅行費用を、親が、婚姻する当事者に対し、出費しているような場合、その費用は特別受益に該当すると判断される傾向にあります。
このような費用は、本来的に婚姻する当事者が支出することが通常であり、親が支出をするだけの合理性(社交上の出費、扶養のための費用)に欠けると考えられるためです。
弁護士にご相談を
挙式費用以外にも特別受益に当たるか否かが争われる費目は多くあります。
また、一般的に挙式費用が特別受益に該当しないといっても、各個別事情によっては、特別受益に該当すると判断されるケースもあります。
「この支出が特別受益に該当するか」という確認だけを裁判所などに確認してもらうことは、判例上できないとされているため、裁判をしてみたものの、特別受益に当たると判断されたことで、相続人間で協議していたときよりも相続分が減ってしまうこともあり得ます。
「この場合の相続財産はどうなるのか」といった疑問は専門的な知識を有する弁護士にご相談して確認することをお勧めします。
(文責・横浜みなとみらい法律事務所)